 戸隠神社・奥社と戸隠山
戸隠神社・奥社と戸隠山
【目 次】
女性に人気があるパワースポット神!
2017年11月15日、私は初めて戸隠神社5社( 奥社・九頭龍社・宝光社・火之御子社・中社)を参拝しました。それから、今までに70以上の神社を訪れ、神社は人気があるんだな〜と思いました。特に30代、40代、50代の女性が多く参拝しています。
人は神様を参拝しているのか、否?
あなたは、アマテラスを始め、神社のご祭神を信じていますか?
イザナギとイザナギをはじめ、アマテラス、ツクヨミ、スサノオの三貴神、オオクニシなど、日本には多くの神様がいらっしゃいます。
しかし、神社に初詣に出かけ、参拝するときに神様の名前とお姿を思い浮かべて、お願いしていますか? たぶん、二拝二拍手一礼したとしても、神様のお名前は唱えていないのではないでしょうか!
わたしはこう考えてみました。神様を信じているのではなく、神社―幽玄な場所にある神社、すなわち「パワースポット=神様」の願掛けているのではないか、と。
パワースポットとは、どんな場所?
『ウィキペディア』には、こう書かれています。
「パワースポット」という言葉は、1975年以降、超能力者を称する清田益章氏が「大地のエネルギーを取り入れる場所」として使いました。この言葉は、1990年代前半から広まったといいます。
荒俣宏氏によるパワースポットの定義
『パワースポットは大地の気がみなぎる場所。古くから、人はその場所で大地の力を得ようとしました』
たとえば「熊野三山詣で」「お伊勢参り」
本来なら厳しい修行を行った者(修験者)がやっと得られる力を、その場所を詣でるだけで得られる、しかも身分性別を問わず簡単に得られると思われている場所がパワースポットです。
ちょっと都合がよすぎませんか!
また、パワースポットと呼ばれている場所は、本来は信仰の場であって自然崇拝が行われていた処です。そういう場所は伝統的に霊場とか聖地などと呼ばれていました。
江原啓之氏は、神社仏閣を「スピリチュアル・サンクチュアリ」と呼んでいます。
そして、2000年頃から大衆向け風水やスピリチュアリズムに対する人々の興味が高まり、神社仏閣などを巡る聖地巡礼ブームも起きてきました。
パワースポット神社の方が仏閣より多い理由?
日本のパワースポットは、神社が圧倒的に多いです。仏閣にパワースポットが少ないのは、若月佑輝郎氏は「仏閣は人々の悩みや悲しみが集まるためパワーが劣っているから」だとしました⁉
しかし、仏閣はそれだけ人々に馴染みが深い場所。人々の心の拠り所になってきたと言えます。
パワースポットは、科学的に説明できるのか?
佐々木茂美氏は、地磁気が打ち消しあう場所ではある状態が発生し、そこに「五次元宇宙」からのエネルギーがもたらされると主張しました。
また、楢崎皐月氏が『静電三法』で土壌中の電位差によって土地自体が持つパワーがあるとし、プラスのエネルギーを持つ「イヤシロチ(弥盛地)」とマイナスのエネルギーを持つ「ケガレチ(気枯地)」が存在するとしました。
また、ケガレチであっても土壌中に木炭を埋設すれば、イヤシロチに変えられるそうです。
経営の神様船井幸雄氏は『イヤシロチ』という本を書いています。また、船井氏は最強金運神社として、富士山にある新屋 山神社と金沢にある金劔宮をあげています。
この二つの神社は、地理上でパワーが強い一直線(レイライン)上にあります。そのレイラインを千葉まで伸ばた安房神社があります。レイラインは、地図上でのパワースポットを考える理由になりそうです。
新屋 山神社、金劔宮、安房神社が、日本三大金融神社です。
パワースポットでの心得と注意点
江原啓之氏はパワースポット・ブームの加熱ぶりに警鐘を鳴らします。神仏への畏敬の念を持たずに、御朱印を「スタンプラリーのように」集めるパワースポット巡りを批判しています。
2010年8月20日のYOMIURI ONLINEの記者が、出雲市佐田町にある須佐神社の神職の困惑をこう伝えています。「数年前まで年間12,000人だった参拝客が、今では100,000人はいるのでは」と話しながらも「携帯のカメラで大杉を撮影するのに夢中で、鳥居や本殿は素通り。神社はお参りするところなのに」と。
神社新報の論説
昨今の「パワースポット・ブーム」などを根柢から否定するつもりはありません。しかし、神社の教化活動の主な目標は、単なる俗的なご利益信仰および特定神社の宣布ではなく、「より広いご神威の発揚とご神徳の昂揚」です。
また、宗教施設の関係者が高名な有識者に対し、自分の神社・仏閣をパワースポットであると紹介するよう依頼する事例があるとの風聞に対し「宗教者自身の資質にも関わる」として、これを批判しました。
「いたづらに流行に飛びつこうという姿勢は慎むべきである」
「話題作りのために、安易に伝統を破壊するような行為だけは、厳に慎んでもらいたい」


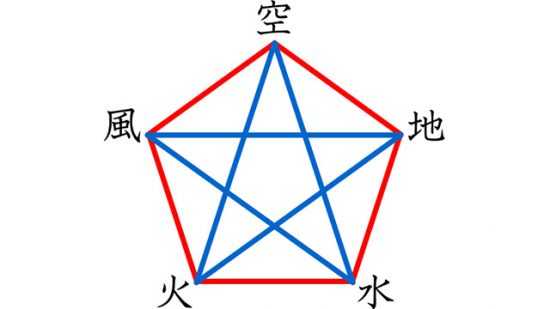
![国内旅行の費用を抑える賢い方法|具体例な節約術[チェック式]](https://hatobus.club/wp/wp-content/uploads/2025/03/costs-down-550x368.jpg)








